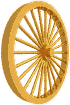以下は、2000年1月にスイスのダボスで開催された世界経済フォーラムのパネルのひとつで、伝統的な実践がいかに教条主義や文化的要素を超越し、宗教の本質を顕現させることができるかというテーマについて、ゴエンカ氏が行ったスピーチの概要である:
今日、私たちがここにつどい、宗教のさまざまな側面について話し合えることをうれしく思います。この宗教、あの宗教ということではなく、宗教そのものについてですね。
宗教には二つの重要な側面があります。その一つが宗教の核心、つまり宗教の真髄であり、これが最も重要です。それは、愛と慈悲、善意、寛容に満ちた道徳的な生活を送ることです。
すべての宗教は本質的に道徳を説いています。これがすべての宗教にとって最大の共通項です。
道徳的な生活とは、体によるものであれ言葉によるものであれ、他者の平和と調和を乱すようなあらゆる行為を慎む生活です。道徳的な生活は、怒りや憎しみ、悪意、敵意といった否定的なものからつねに自由です。
道徳的な生活は真の宗教的生活です。そこでは人は自らの内なる平和と調和のうちに生き、他者に対しても平和と調和以外の何ものをも生み出しません。
真の宗教的生活は「生きる技」であり、道徳的な行動規範であり、幸福で調和のとれた健康的で健全な生活です。真の宗教的生活は、自分自身にとっても、他者にとっても、そして人間社会全体にとっても、つねに良いものです。
真の宗教者とは、敬虔な人、道徳的な生活を送る人、よく統制された規律ある心を持つ人のことです。思いやりと慈悲に満ちた純粋な心を持つ人のことです。真の宗教者は人間社会にとってかけがえのない宝です。このような真の宗教者は、国やコミュニティ、肌の色、性別を問いません。裕福でも貧しくても、教育があってもなくても、関係ありません。すべての人間は真の宗教者になることができるのです。
よくコントロールされた規律正しい心、愛と思いやりに満ちた純粋な心を持って道徳的な生活を送ることは、どの宗教の専有物でもありません。それはすべての人のためのものです。それはすべての宗派の壁を超越します。それはつねに非宗派的です。それはつねに普遍的です。それはつねに包括的なものです。
人びとがこの宗教の真髄を実践するならば、信仰する宗派が異なっていても、世界中の人びとの間で対立や争いが起こる理由はなくなります。人間社会の誰もが、この宗教の真髄を守ることによって、真の平安、真の調和、そして真の幸せを享受することができます。
しかし、宗教にはもう一つの側面があります。それは宗教の外側の殻です。そこには儀式や儀礼、祭礼などが含まれ、それはさまざまなカルトに変質する可能性をもっています。それぞれが独自の神話的、哲学的信念をもち、それはドグマや盲目的な信仰、盲目的な信念に変質する可能性があるのです。
道徳という内なる本質が共通しているのとは対照的に、この外殻は大きな多様性を示します。あらゆる組織宗教や宗派は、それぞれ独自の儀式、儀礼、祭礼、信念、教義などを持っています。それぞれの組織宗教や宗派の信者たちは、通常、自分たちの儀式、儀礼、信仰、教義こそが救済への唯一の手段だと考え、それらにきわめて強い執着を抱くようになります。このような誤った考えを持つ人びとのなかには、道徳性や他者への愛情、思いやり、善意を少しも持っていないにもかかわらず、特定の儀式や儀礼を行ったから、あるいは特定の信仰を完全に信じているからという理由で、自分は信心深い人間なのだと思い込んでいる人がいます。実際には、そのような人びとは自分自身を欺き、宗教の真髄を実践することで得られる甘露を見逃しているのです。
そしてこの外殻のもっとも悪い部分は、次のようなもの。
自分の信仰に強い執着を持つ人びとは、他のすべての組織宗教の信者は背信者であり、そのためけっして救済を得ることはないという確固たる信念を持っています。彼らは、他者を自分の宗教に改宗させることが大きな功徳を積む行為だと確信しており、そのためにさまざまな強制的な方法を用います。
さまざまな組織宗教の信者たちによる、このような盲目的な信仰は、狂信的な原理主義に変質しやすく、論争、矛盾、暴力的な対立、さらには戦争や流血へと発展し、社会に莫大な苦しみをもたらし、平和と調和を奪い去ります。そしてこれらすべてが宗教の名のもとに行われています。人間社会にとってなんという不幸でしょうか。
宗教の外殻が重要視されるようになると、道徳という内なる本質が失われてしまいます。
それがどれほど望ましくないものであっても、この固い外殻なしには宗教は存在し得ないと人びとは感じることがあります。しかし、この外殻をまったく関係ないものとして無視し、道徳という内なる本質に100パーセントの重要性を置く試みは、過去に成功を収め、今日でも行われています。この実践を成功させる方法こそが、ヴィパッサナー瞑想と呼ばれるものなのです。